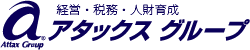「問題のある社員だからといって、すぐに解雇できない」
「人手不足の昨今、優秀な人材や将来性のある人材の離職は絶対に避けたい」
経営者や人事担当者の皆様は、日々、人材管理・マネジメントにおける難しい判断を迫られていることと思います。
職場におけるハラスメントは、これらの課題に深く関わっています。ハラスメントが横行する職場環境は、社員のモチベーション低下や離職率上昇を招き、必要な人材を手放す大きな要因となりかねません。
また、ハラスメントの問題を起こした社員への適切な対応を怠ると、企業は訴訟リスクに晒されるだけでなく、イメージを大きく損なう可能性もあります。
本コラムでは、ハラスメント対策の重要性をあらためて見つめ直し、企業が取り組むべき具体的な防止策や発生時の対応について解説します。
社員が最大限に能力を発揮できる職場環境を構築し、優秀な人材を惹きつけ定着させるヒントとなれば幸いです。
ハラスメントとは
ハラスメントとは、一般的に相手を不快にさせたり、嫌がらせをしたりする行為全般を指します。
職場におけるハラスメントは、社員の尊厳を傷つけ、活躍を妨げるだけでなく、組織の生産性低下や訴訟への発展にも繋がりうる深刻な問題です。
また、職場におけるハラスメントの種類は様々です。代表的なものとして、以下が挙げられます。
| パワーハラスメント | 職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与える行為 |
|---|---|
| セクシャルハラスメント | 相手の意に反する性的な発言や行動により、相手に不快感を与える行為 |
| ジェンダーハラスメント | 性別に対する固定観念や偏見に基づいた発言や行動により、相手に不快感を与える行為 |
| モラルハラスメント | 言葉や態度によって、相手の尊厳を傷つけたり、精神的に追い詰めたりする行為 |
| マタニティハラスメント | 妊娠・出産・育児に関する制度の利用を阻害する言動や、解雇・降格などの不利益な取り扱いをする行為 |
これらの他にも、パタニティハラスメント、ケアハラスメント、アルコールハラスメント等々、法令によって定義されているものやそうでないものを含め、多くの言葉が登場しています。
それだけ世間が関心を持っているテーマと言えるのではないでしょうか。
パワハラ防止法で義務付けられた措置とは
2020年6月、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が施行され、企業規模に関わらずパワーハラスメント防止措置が義務化されました。
具体的には、以下の4つの措置です。
事業主の方針等の明確化および周知・啓発
パワハラ防止法では、企業に対し、職場におけるパワハラの内容や、パワハラをしてはならないという方針を明らかにし、社員に周知・啓発することを求めています。
また、就業規則にパワハラに関する規定を明記することも義務としています。
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
社内外に相談窓口を設置し、社員に周知する必要があります。また、相談窓口の担当者が適切に対応できるよう、企業としてフォローしなければなりません。
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
職場におけるパワハラについて、相談を受けた際の速やかな事実関係の確認が義務として示されています。
ハラスメントが認められた場合、加害者・被害者に対する措置も講じなければいけません。また、事実確認の結果にかかわらず、再発防止に向けた対応が求められます。
そのほか併せて講ずべき措置
上記に加えて、当事者のプライバシー保護の措置や、その周知が必要ですまた、ハラスメントについて相談したことを理由に不当な扱いを受けないことを定め、周知する旨が義務とされています。
※出典:厚生労働省「2020年(令和2年)6月1日から、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf
ハラスメント発生時に企業は何をすべき?

ハラスメントが発生してしまったとき、企業として迅速に対応することが肝心です。
では、実際にどのように対応するべきでしょうか?手順を考えてみましょう。
状況の把握
ハラスメントが発生した場合、まずは状況を把握することから始めましょう。
相談者の安全を確保し、必要に応じて休職や配置転換などの初期対応を検討することが大切です。
事実確認およびハラスメントの判断
次に、事実関係の確認を行います。関係者へのヒアリングや証拠収集を行い、客観的な視点から事実関係を明らかにします。
感情的な判断は避け、公平な立場で調査を進めなくてはなりません。収集した情報に基づき、ハラスメントの有無を慎重に判断します。
当事者への処置
ハラスメントが認められた場合、就業規則に基づき、加害者に対して適切な処分を行います。
また、被害者の精神的なケアを行い、休職している場合は円滑な職場復帰を支援することが重要です。双方への配慮を欠かさないようにしましょう。
再発防止措置
最後に、ハラスメント発生の原因を分析し、再発防止策を策定・実施することで、同様の問題が再び起こらないように対策を講じます。
相談者、加害者、状況次第では関係者に対して、対応状況や結果を適切に情報共有することも重要です。
ハラスメントを防ぐための4つの対策
ハラスメントを未然に防ぐには、トップのコミットメントと、全社員の「ハラスメントを許さない」という強い意識が欠かせません。
対策は単なる義務ではなく、社員一人ひとりが尊重され、心身ともに健康に働けるための投資と捉えるべきでしょう。
以下を参考に、皆様の会社でも方法を検討してみてください。なお、対策は一度実施したら終わりではなく、継続的な見直しや改善が必要です。
社員の意識改革や研修
役員を含む全社員に対し、ハラスメントに関する正しい知識を習得するための研修を実施することが望ましいです。
研修では、ハラスメントの定義、種類、事例、および発生した場合の影響について理解を深めるだけでなく、加害者にならないための行動指針、被害者になった場合の相談方法などを具体的に伝えましょう。
コミュニケーションの活性化
風通しの良い職場環境には、コミュニケーションの活性化が必要です。
1on1ミーティング、チームビルディング研修、社内イベントの開催など、上司と部下、社員同士が気軽に意見交換できる機会を設けてはいかがでしょうか。
オープンなコミュニケーションを促進することで、ハラスメントの兆候を早期に発見しやすくなります。
相談窓口の設置および機能強化
従業員が安心して相談できる窓口を整備し、周知することも重要です。より相談しやすい状況を作るため、社内だけでなく、外部機関と連携することも有効な方法の1つです。
なお、相談者のプライバシー厳守し、適切な対応ができるよう、相談担当者の選任や教育は慎重・丁寧に行わなくてはなりません。
定期的なヒアリング
従業員のハラスメントに関する意識や実態を把握するために、定期的なヒアリングを実施しましょう。
アンケート調査やストレスチェックを活用し、調査結果を分析することで、課題の特定や改善に繋げられます。
また、ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を雇用する事業場で義務化されています。
まとめ

いかがでしたか?ハラスメント対策は、企業が健全な組織運営を行う上で不可欠です。自社の状況に合わせた適切な対策を講じ、誰もが安心して働ける職場づくりに取り組みましょう。
アタックス・ヒューマン・コンサルティングでは、ハラスメント発生時のチェックリストを無料で配布しています。
ハラスメント発生時はもちろん、会社やチームとして対策を講じる際の参考として、ぜひご利用くださいませ。
筆者紹介

- 株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング 社会保険労務士 コンサルタント 三苫 芽以
- 福岡県出身。大学卒業後、アパレル企業に就職し、店舗での接客・販売に従事。その後、IT・Web 業界の企業で新卒中途採用、総務等をおこなう中で、「社員が精神的・物理的に安心して働ける土台があってこそ、企業はより成長できる」と実感する。 強くて愛される会社を増やすべくアタックス・ヒューマン・コンサルティングに入社し、企業人事の実務経験を活かした支援ができるよう奮闘中。休日は運動不足解消のため、ピラティスに励んでいる。