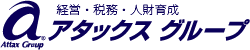ここ数年、賃上げの波が止まりません。
厚労省によれば令和6年の民間主要企業の賃上げ率は5.33%と33年ぶりの高水準で、大卒初任給も24.8万円まで上昇しています。
参考:厚生労働省「令和6年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況を公表します」
令和7年の調査結果は未公表ですが、これを上回る水準になることが容易に想像できます。
過去30年の経済停滞を異常な状態だと捉えれば、昨今の賃上げ気運はある意味では正常な変化とも捉えられますが、実質賃金はマイナスであり、この賃上げ水準でも、物価上昇率には及んでいません。
経済成長の結果ではなく、円安等による物価高が進んだ結果、必要に駆られて賃上げ気運につながっている状況にあると言えます。
当然ながら、企業において付加価値が上がらない状態で賃上げすれば減益になります。
このような状態は、いずれ限界を迎え、名目賃金すらも上がらなくなっていくでしょう。
これからも日本が永続していくためには、社会全体で賃上げを行うこと、そしてそれ以上に、付加価値の向上を実現していくことが必須でしょう。
労働人口の7割の働き先として、日本を下支えしているのが中小企業の皆様です。
各企業の経営者が、賃上げと付加価値向上をセットで考えていかなければなりません。
「防衛的賃上げ」から「前向きな賃上げ」へ
賃上げは主に2通りの形があります。
一つは、会社・業績の成長により増加した付加価値を社員に還元する形で行う、いわば「前向きな賃上げ」。
もう一つは、成長は見られないものの、労働市場での競争力確保のために、世間動向を受けて行う「防衛的賃上げ」です。
前向きな賃上げが理想的であるのは言わずもがな、時には世間動向を見て防衛的に賃上げを行う必要もあります。
しかし、毎年受け身な賃上げに終始するのみでは、固定費比率が膨らみジリ貧に陥ってしまいます。
賃上げが先行したとしても、付加価値向上への施策を打ち、前向きな賃上げへの転換を狙っていくことが大切です。
付加価値向上のためには、既存事業を進化させるのか、あるいは新規事業に打って出るのかなど、様々なアプローチがありますが、いずれの場合も企業活動の源となる社員の活躍が欠かせません。
その活躍を促すために、賃上げなどの各種人事施策を行うことが大切なのです。
トータルリワードでの報酬感の維持・向上

付加価値向上のため、社員の活躍を促すには、何をすべきでしょうか。
OJTの実施や作業設備の改善など、打ち手は無限にあるでしょう。
ただどんな素晴らしい制度・環境を整えても、活躍する社員本人が行動に移さなければ、成果につながりません。
何をするにも、社員が行動に移すよう、「動機づけ」を促す視点が必須です。
そのための重要な視点の一つとして、社員が求める「報酬」を用意するということが挙げられます。
主な報酬として皆様がイメージするのは「給与」でしょう。給与は新規採用や長期勤続を促す上で、非常に重要な要素です。
特に、賃上げが加速している昨今は、一定の昇給水準を確保しないと社員に報酬感(頑張りが報われているという実感)を与えることは困難です。
しかし、価値観が多様化している現代においては、給与以外の非金銭的報酬をも含めた「トータルリワード」の考え方が欠かせません。
給与だけでなく
「自由な場所・時間・服装で働ける」
「業務時間外で社員と交流できる」
「きれいなオフィスで働ける」
といった、働き方やコミュニケーションの形も報酬になり得ます。
また、
「自身の専門性を深める仕事ができる」
「社会的使命に応える仕事ができる」
など、仕事そのものも報酬の一部になります。
一方で、
「きちんとスーツを着て会社で仕事したい」
「専門性ではなく広い業務知識を得たい」
「ルーティン業務をしていたい」
といった、前述とは異なる価値観が、人によっては報酬になり得るという点にも留意する必要があります。
したがって、賃上げが必要とお考えであっても、一度、本来の目的に立ち返り、
「そもそも社員が魅力に感じる報酬とは何か」
「会社はその魅力的な報酬を提供できているか」
を明らかにした上で、
「どの魅力を向上させるか(例:給与、福利厚生、教育研修等)」
「どのように向上させるか(例:賃上げ、賞与増額、社員旅行実施等)」
を検討する必要があると考えます。
当然、生活保障のために一定水準の給与は必要ですが、それはあくまでもトータルリワードの一部に過ぎず、賃上げは、報酬に対する納得感や満足感を維持・向上させるための一手段にすぎないのです。
賃上げで起こりがちなトラブル
トータルリワードの考え方も踏まえた上で、賃上げの方法を検討していきましょう。
賃金水準の良し悪しは業種業界企業規模によって様々ですので一概に評価できませんが、「賃金構造基本統計調査」「就労条件総合調査」といっ厚生労働省統計調査による同業平均などが一つの目標となります。
しかし、ここでも賃金表とにらめっこしているだけではいけません。
実際、賃上げでは以下のようなトラブルが起こりがちです。
採用市場で戦えるように、賃金表のスタートを変え、新卒初任給を○万円上げた。
結果、
⇒既存社員との給与の逆転が生じ、離職が増加した
⇒新卒社員のその後の昇給が抑えられ、入社間もなく離職してしまった
トレンドに合わせ、賞与原資を月給に振ることで賃上げを行った。
結果、
⇒賞与額の低さで不満が爆発し、離職が発生した
⇒賞与の増減での人件費調整がしにくくなり、営業利益を圧迫してしまった
安易な基本給表の書き換えは避け、別途手当を新設して賃上げした。
結果、
⇒手当が乱立してしまい、社員から見て、何を以ってどれだけの給与が支給されているかが、一見してわからない状態に陥った
在宅勤務の増加に合わせ、オフィスを縮小して固定費を削減し、社員の給与に還元した。
結果、
⇒社員のコミュニケーション機会がさらに減少し、生産性低下・離職につながった
これらの対応は、検討手法次第ではいずれも有効に作用するものですが、目先の人件費負担や賃金制度のみを対象に検討を進めると、社員の動機づけにかえって悪影響を及ぼすこともあり得るのです。
賃上げの直接的実務は、賃金制度の改定ですが、それだけでなく、そもそも社員が何を求めているのかを明らかにしたうえで、賃上げの根拠になる「評価」、評価の基準となる「等級制度」にまで目を向け、人事制度全体のチェック・整備を行っていくことが必要です。
おわりに

前述の動機づけの考え方は、再現性が証明されている期待理論に基づき、「ヒトキラメソッド」という形で弊社が提唱しているものの一部です。
社員が生活を維持できる水準での賃上げは確保しつつ、社員の動機づけのための多様なアプローチも選択肢に入れながら、今後の人事施策を検討されてはいかがでしょうか。
賃金一辺倒にならない報酬のあり方にご関心をお持ちでしたら、ぜひいつでもこちらからご相談ください。
筆者紹介

- 株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング コンサルタント 嶋津 紘太
- 関西大学社会安全学部卒。大学でリスク管理を専攻する傍ら、アルバイトで長時間労働や杜撰な勤怠管理などの労務問題に直面。これをきっかけに、企業の「人」にまつわるリスクの低減に寄与することを目指し、アタックスに新卒入社。入社以来、人事制度構築・運用、人事労務顧問、教育研修講師業務に従事。国内大手重工業グループから少数精鋭のオーナー企業まで、規模・業種を問わず、幅広い企業の経営者・人事責任者・管理職を対象に継続的な支援を行っている。近年は中小企業に最適化した人事制度構築モデルの開発に注力。企業規模に関わらず社員が輝ける仕組みを作るべく、運用可能性第一の人事制度設計をクライアントに提案・実行中。