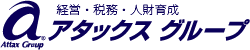帝国データバンクの調査によりますと、2025年上半期(1〜6月)の人手不足倒産は202件にのぼり、上半期としては2年連続で過去最多を更新しました。
出典:帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査(2025年上半期)」
https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250704-laborshortage-br25h/
さらに、Sansan株式会社が同年8月に実施した中小企業向けの調査では、回答企業の半数以上が営業の人手不足を実感しており、そのうち約8割の経営層が「売上の停滞・伸び悩み」を課題として挙げています。
複雑化する市場環境と人材不足が重なることで、多くの中小企業が成長の鈍化に直面し、営業組織の限界を痛感している状況です。
現場が「未来の売上づくり」に手を回せない理由
私の所属するアタックス・セールス・アソシエイツは、企業の営業現場に入り込み、目標達成を支援する専門部署です。
売上見通しの不透明さに人手不足が重なることで、現場では短期的な営業活動、すなわち既存顧客からの引き合いを確実に受注につなげることにリソースが集中しがちになります。
その結果、経営は営業に未来の成長を見据えた活動を期待しているにも関わらず、新規顧客の開拓や営業戦略の構築といった中長期的な成長を支える活動が後回しになってしまいます。
営業は「日々の数字を追うだけで精一杯」になっており、「未来の売上をつくる活動」に手が回らなくなっているのです。
人を増やすだけでは成果につながらない
しかし、営業人員を増やせば問題が解決するかといえば、そう単純ではありません。
確かに、既存顧客対応の手は足りるようになるかもしれませんが、既存ビジネスをこれまで通りに続けていては、売上や利益の減少は避けられません。
加えて、人員が増えれば当然、生産性が下がるリスクは増大します。
また新規ビジネスの創出や新市場の開拓においては、既存顧客の属性やサービスの特徴、提供してきた価値など、自社が積み上げてきた資産への深い理解が不可欠であり、単なる人数の多寡では、成果にはつながりません。
売上停滞を打破する「体制づくり」の4つの要素
引き合い対応を前提にした「人手」を埋めるための採用活動ではなく、まず整えるべきは「新たな顧客・仕事を生み出す体制」です。
以下の4つの要素が、売上停滞を打破する営業組織の再構築、すなわち「体制づくり」において重要なポイントです。
明確な目標設定
歴史ある技術力の高い企業ほど、既存顧客からの引き合いが多く、現時点からできることを積み上げる「順算思考」に陥りがちです。
目標も戦略も出来ることを出来る範囲で行う経営に成長の余白はありません。
組織全体の意識改革を目指すには、これまでの発想の延長線上にはない高い目標に取り組む意義を明確にし、全社でその重要性を共有することが第一歩となります。
ターゲットの分析と選定
市場や顧客の構造が多様化・細分化する中で、「どの領域に勝機があるか」を見極めるには、現売上を起点に考えてはいけません。
目に見える実績や引き合いでなく、これからの拡がる可能性のある顧客、商材のポテンシャルを分析し、優先的に活動する先を選ばねばなりません。
そのためには営業自身が営業現場の情報をデータ化し、仮説検証を繰り返す論理的な思考力を持つことが必要です。
従来型の“経験と勘”に頼る営業手法では、もはや通用しません。
行動する組織習慣
高い目標を設定しターゲットを明確にしたところで、営業が機を逃さずアプローチしなければなりません。
また、引き合い対応を中心とする多くの企業では、同一のターゲットに対して3か月以上、継続的にアプローチし続けることは殆どありません。
引き合い対応に慣れすぎた弊害で、1度や2度の反応の悪さですぐ諦めがちです。
新規開拓には継続性が不可欠であり、心理的負荷の高い活動でも「やらない、遅い、続かない」が習慣化している組織では成果は望めません。
「行動する組織習慣づけ」こそ、現場指導で最も力を入れるところです。
営業プロセスの再構築
営業プロセスそのものの再構築も不可欠です。
前述の通り、新規開拓には、見込み客の発掘から関係構築、提案、成約まで長い時間がかかります。
引き合い中心が根付き、短期的な成果を求める文化が根強い企業では、長期的に成果を出すためのプロセスそのものが失われている事が少なくありません。
そのため、KPI(重要業績評価指標)の設定や人事評価制度の見直し、プロセスの進捗を正当に評価できるマネジメントの仕組みを再構築する必要があります。
「人手不足」は構造的課題である

これらの要素は、いずれも新たな顧客・仕事を生み出すための体制づくりに欠かせないものです。
新しい取り組みは一朝一夕では成果が出ません。時には数ヶ月、あるいは年単位の投資が必要となります。
短期的な数字だけを追うマネジメントでは、組織が疲弊してしまいます。経営層や営業リーダーには、「長期的な成果を信じてやり切る覚悟」が求められます。
営業の人手不足は、単なる人数の問題ではなく、営業の構造的課題であると捉えるべきです。
人が足りないから成果が出ないのではなく、成果を出すための体制が整っていないから人が疲弊していく。
こうした悪循環が、今、多くの企業で起きています。真に取り組むべきは営業人員の確保以上に、売上を上げるための道筋を定めることです。
人を増やす前に、仕組みを見直し、体制を整える決断こそ、「売上の停滞・伸び悩み」を課題解決するために必要なのではないでしょうか。
筆者紹介

- 株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ 取締役副社長 桑原 賢一
- 大手化粧品メーカーを経て、アタックスへ入社。BtoC、BtoB双方に豊富な営業現場経験を有している。現職では、目標予算を達成させるマネジメント手法「予材管理」を駆使し、上場企業の営業戦略構築・幹部マネジャー育成から、中堅中小企業では現場直接指導まで企業状況にあわせ豊富な指導スタイルを持つ。市場環境変化によって凋落した企業の組織を鍛え上げ、競合を圧倒するまでの状態に引き上げ、本業での会社継続は難しいとまで判定された企業を地域No.1まで立て直す、など数多くの指導実績から企業規模、業界業種を問わず多くのクライアントから支持されている。このためクライアントからの継続依頼率は群を抜いており、現在ではセミナー・講演は殆ど行わず、現場指導を中心に活躍する実践派・実力派のコンサルタントである。