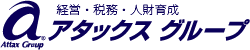オンラインツール活用に向けた国税庁の取り組み
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、対面機会を抑制することを目的に、Web会議システム等のオンラインツールを利用した調査対応を要請されるケースが大企業を中心に多く認められておりました。
このため、税務行政のDXの推進の観点からも、納税者の皆様の理解を得ることを前提として、大規模法人を対象に、調査又は行政指導におけるオンラインツールの利用を試行的に実施しています。
出典:調査等におけるオンラインツールの利用(試行)について|国税庁
これは、令和6年7月に国税庁から出された「調査等におけるオンラインツールの利用(試行)について」の概要です。
また、令和7年6月16日に国税庁より税理士会宛に出された「調査等におけるオンラインツールの利用等について(周知依頼)」では、以下のように示されています。
令和7年9月から、調査等を実施する際に、必要に応じてオンラインツール(インターネットメール、Web会議システム(Microsoft Teams)又はオンラインストレージサービス(Prime Drive))を利用することを順次予定しております。
この取組は、税理士業務におけるデジタルの活用にも資するものと考えておりますが、利用に当たっては一定の手続を行っていただく必要があります。
さらには、令和8年6月末までに、上記のツールを活用するための端末が、国税局の全職員に一人一台配備されるとのことです。
税務行政DXの全体像と三本柱
一見すると、今回の通知は、税務調査におけるオンライン対応や証憑類のデジタル提出といった、アナログからデジタルへの業務移行を周知する内容に見受けられますが、果たしてそれだけでしょうか。
遡ること2年前、国税庁は令和5年6月23日に「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション―税務行政の将来像 2023―」を公表しました。
この中で、以下の三本柱を軸とした税務行政の目指す方向性と、今後の具体的な取り組みが示されています。
①納税者の利便性の向上
②課税・徴収事務の効率化・高度化
③事業者のデジタル化促進
出典:税務行政のデジタル・トランスフォーメーション―税務行政の将来像 2023|国税庁
二本目の柱である「課税・徴収事務の効率化・高度化」のうち、「課税事務」では、上記の「調査等におけるオンラインツールの利用」に関連し、個別・具体的な施策が本年9月から順次実施される、とあります。
それでは、これらの個別・具体的な施策について確認してみましょう。
まず、「データの活用の徹底」が大きな方針として掲げられおり、そのうえで、次の4つの区分に分けて具体例が示されています。
①AI・データ分析の活用
②オンラインツール等の活用
③関係機関への照会等のデジタル化
④税務データの学術研究目的の活用
このうち、④を除く①~③については、調査業務との関連が深いため、それらの内容を確認していきます。
まず、①「AI・データ分析の活用」では、課税の分野において、AIを活用して幅広いデータを分析し、申告漏れの可能性が高い納税者の判定が行われています。
次に、②「オンラインツール等の活用」として、Web会議システムの導入や、電子的な調査通知の活用などが挙げられます。
さらには、③「関係機関への照会等のデジタル化」では、納税者から提出される決算書や申告書の他、第三者から提供される情報や実地調査時のデータなどが、分析用に加工され活用されています。
要するに、AIによって申告漏れや計算誤りの可能性が高い納税者を『的確に抽出する』ということです。
AIがもたらす調査の精度向上と影響
AIによる的確な抽出は、これまでと大きく異なる点であり、間違いの発見確率や精度が大幅に向上することで、税務行政の効率化に飛躍的に貢献すると考えられます。
ただし、抽出された納税者のうち、調査の必要度が高い納税者に対しては実地調査が行われ、それ以外の納税者に対しては書面や電話による行政指導に留めるという流れは、従来と大きく変わらないものと思われます。
ここで、もう一つ確認しておきます。
電子帳簿保存法の改正やインボイス制度の導入は、三本目の柱の「事業者のデジタル化促進」の取り組みの一環であることにお気づきでしょうか。
電子帳簿保存法の改正では、電子取引に関する電子データの保管が義務化されました。
また、インボイス制度では、電子インボイスからデジタルインボイスへと進化し、さらにPeppolインボイスや全銀EDI(ZEDI)を活用したデジタル化による一貫した事務処理のプラットフォームもすでに整備されています。
つまり、インボイス制度もまた、しっかりとデジタル化が進んでいたのです。
もちろん、消費税の仕入税額控除を目的とした制度であることに、変わりはありません。
納税者に求められる対応と備え
この税務行政のDX、つまりデジタル化の流れを、納税者の立場から俯瞰するとどう映るでしょうか。
AIによって調査の必要性が高い納税者として抽出されないためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか?
自社の決算書や申告書については、事前にAIによるチェックも可能な気がしますが、第三者から提供される資料や、実際に税務調査で得られる情報など、さまざまなデータも同様に入手するのは難しいため、あれこれ考えても仕方がないことかもしれません。
例えば、AIによって抽出された結果、調査が実施され、自社の会計処理に関するデジタルデータを求められた際、それをそっくりそのままアップロードしたとします。
このアップロードしたデジタルデータにも、AIが活用されると考えておく方がよいでしょう。
証憑に基づく会計関連書類との日付や金額の突合チェックなどAIに任せない手はありません。
具体的には、交際費の中で特定の取引先に関し、摘要欄が空欄だったり、同じ内容が毎月繰り返されているものを抽出したり、契約どおりに取引が行われているか、また、取引どおりに記帳されているかを、瞬時に正確に判断することは容易に想像できます。
これまでの調査は、金額の多い順やサンプル抽出など、人手による事務効率性を重視していましたが、AIによる調査は、より厳格で容赦ない可能性があります。
ただし、AIを活用するか否かによって、会計処理済みの内容そのものが変わるわけではありません。内容が正しければ、根拠を示して説明できればよいのです。
説明するためには、自社の取引実態や業務の流れをしっかり理解しておかなくてはなりません。
これはこれまでと同様、説明責任という観点からも、今後も変わらないでしょう。
たとえ、デジタル化が進み処理の自動化が実現したとしても、自社の処理の流れやその結果の正確性については自ら確認できる体制を維持していただきたいと思います。
自社の経営課題について、顧問税理士などの専門家を相談相手にされている納税者も少なくないと思います。

税務調査におけるオンラインツールやAIの活用へと税務当局が舵を切ったことを機に、改めて顧問税理士などと自社の会計処理の流れや処理結果の正確性について、税務調査の場面を想定しながら、ご相談されてみては如何でしょうか?
なお、現時点での調査等におけるオンラインツールは、積極的に活用するとされており、納税者の同意(同意書の提出)が前提となっています。
また、実地調査がなくなるとは現時点で言及されていません。
税務行政のデジタル化は納税者と税務当局双方にとって新たな挑戦ですが、正確な記録の管理と専門家との信頼できる対話を通じて、安心・円滑な納税環境の構築を目指していくことが重要です。
専門家と一緒に準備を進め、よりスムーズな税務対応を目指しましょう。
筆者紹介

- 株式会社アタックス クラフトパーソンズ・センター 経営支援責任者 税理士 入駒 慶吾
- 専門学校講師、税理士事務所勤務を経て、アタックス税理士法人に入社。課題解決型の税務顧問・経営顧問に従事。「傾聴と共感」をモットーに、顧客中心主義の税務サービスを提供しながら、抜群の指導力を発揮する。お客様に寄り添い、供に課題解決していく姿勢に定評がある。