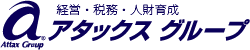企業に関係する誰をも犠牲にしない経営をするためには、徹底した差別化経営が重要です。
受注の大半が、相見積もりや競争見積もりを経て、ようやく確保した仕事をメインとしても、社員とその家族をはじめとした5人(者)の幸せ、5方良し経営の実現は不可能です。
このことは、モノづくり産業だけでなく、商業やサービス業でも同様です。
顧客の大半が「たまたま客」や新規の許可油が増加しない「地域内の固定客」ばかりであったならば、企業経営は不安定になるばかりか、じり貧になることは目に見えています。
5方良し経営の実現のためには、顧客の大半が「わざわざ客」「全国区の固定客」「ファンのような顧客」であることが必要不可欠なのです。
わが国企業の99.7%を占める圧倒的多数派である中小企業が、こうした、ファンづくり経営による差別化経営を実現するためには、まずは、何のために・誰のために、自社は存立しているのかといった、そもそも論・あり方の理解と認識が必要です。
というのは、どんなに優れた商品力や技術力、あるいはマーケティング力があったとしても、それを使う市場・顧客が間違っていれば、大して役に立たないからです。
それはまるで、世界一の名刀であっても、遠く離れたピストルをもった相手には到底勝てないのと同じなのです。
つまり、多くの中小企業は、戦略論、つまり経営の「やり方」をどうするかといった前に、経営の「あり方」の誤解があるやに思えてなりません。
その1つが、大企業と中小企業の違いに関する議論です。
多くの人々は、大企業と中小企業の違いは規模の違いであるとか、資本力の違いであるなどといいますが、筆者の理解認識はそうではなく、生きる世界が根本的に異なる生物と考えます。
両者を魚に例えるならば、大企業とは、深い・広い海で生きる、クジラのような生物であり、一方、中小企業は浅瀬・狭い海で生きる、ボラのような魚といってもよいでしょう。両社は生存領域が全く違うのです。
それゆえ、深い広い海で生きるべき生物が、浅瀬や狭い海に来たならば、大半が死んでしまいます。
逆に、浅瀬やクジラが入り込めないような狭い海で生きるべき生物が、深い広い海に行けば、大きな生物にたちまち食べられてしまうのは当然なのです。
これを経営学的に言えば、大企業は、大量生産・大量販売が求められている大きな市場が生存領域であり、一方、中小企業はその逆で、ロットの小さい、顧客の顔の見える市場、より具体的に言えば、「多品種少量・多品種微量」の市場こそが生存領域なのです。
しかしながら、多くの中小企業は、誰にも迷惑をかけず、経営を持続させていくためのこうした原理・原則を守らず苦しんでいるといっても過言ではありません。
ロットが小さいとか、短納期であるとか、手間暇かかる面倒な仕事であるといって、避けるような経営をしている企業が多いのです。そして、量や無人化・省人化の可能性の高い仕事を選ぶのです。
その結果はというと、製造業であれ、建設業であれ、物流業であれ、あるいは流通業であれ、中小企業の多くは、大企業に依存・追随したかのような経営に陥ってしまっているのです。
そして、受注量や受注単価に、日夜悩まされているのです。
そればかりか、本来、共存的競争をすべき仲間である中小企業同士が、仕事欲しさのあまり、過当競争状態に陥り、取った・取られたといった「喧嘩ビジネス」に陥ってしまっているのです。
加えて言えば、中小企業同士が低単価競争をし、市場や発注者が要求していないような低単価で受注をし、利益なき繁忙をし、自らの首を絞めていると思われる中小企業も少なからずあります。
こうした中にあって、中小企業の生存領域を愚直に守り、顧客から圧倒的な支持を受けている中小企業も、全国各地に少なからずあります。
その1社が、「有限会社万年筆博士」という小規模企業です。所在地は、鳥取市の鳥取駅前商店街の一角にある社員数は家族のみの3人という企業です。
主製品は、社名の通り、万年筆です。こう言うと、全国どこにでもある万年筆の仕入れ販売の小売商店かと言われそうですが、全く違います。
同社の仕入れ商品はゼロ、同社が販売しているすべての万年筆は、全て同社が手づくりで製造し販売しているからです。
製造販売している万年筆の全ては受注生産で、正にこの世に1本しかない自分だけのオリジナルな商品なのです。こうした企業経営が国内だけでなく、今や海外からも評価され、海外顧客は約半数、納期も1年以上先です。
同社の創業は1944年、現代表である山本竜氏は3代目です。創業当初は、大手ブランドメーカーの開発製造している万年筆をはじめとした文具の仕入れ小売りと文具の修理を主事業としていました。
しかしながら、その後、ボールペンの拡大やアジアの国々からの低価格万年筆の輸入、さらには、いわゆる流通革命等が相まって差別化できず、年々経営の持続な困難になっていったのです。
こうした中、「このままでは潰れる…」と危機意識を募らせ、今日のオリジナル市場に事業転換をしたのです。(詳細は同社のホームページを見ていただきたい)
こうした中小企業の生存領域を頑なに守り、価格競争をしない中小企業が多数になれば、わが国中小企業の未来は明るい。
アタックスグループでは、1社でも多くの「強くて愛される会社」を増やすことを目指し、毎月、優良企業の視察ツアーを開催しています。
視察ツアーの詳細は、こちらをご覧ください。
筆者紹介

- アタックスグループ 顧問
経営学者・元法政大学大学院教授・人を大切にする経営学会会長 坂本 光司(さかもとこうじ) - 1947年 静岡県生まれ。静岡文化芸術大学文化政策学部・同大学院教授、法政大学大学院政策創造研究科教授、法政大学大学院静岡サテライトキャンパス長等を歴任。ほかに、「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞審査委員長等、国・県・市町村の公務も多数務める。専門は、中小企業経営論、地域経済論、地域産業論。これまでに8,000社以上の企業等を訪問し、調査・アドバイスを行う。