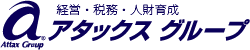思い込みを超えた経営判断の必要性
経営の現場において、直感や経験に基づいた判断が重要であることは言うまでもありません。
しかし同時に、私たちは誰しも「思い込み」というバイアスから逃れられない存在でもあります。
そのため、客観的な「計数」に基づく意思決定は、ますます必要とされていると私は考えています。
経営の羅針盤としての会計
京セラ創業者・稲盛和夫氏は、自身の経営哲学を記した著書『稲盛和夫の実学』の中で、会計は「経営の羅針盤」であり、経営者が目標に向かって正しい航路を取るために欠かせない「計器」であると述べています。
まるで飛行機の操縦席にあるメーターのように、数値が示す情報を的確に読み取りながら経営の舵を取らなければ、どんなに高い志を持っていても、企業は迷走してしまう。
稲盛氏の言葉は、経営における“計数の意義”を本質的に捉えています。
認識と実態のギャップ
私自身もこの考えに深く共感しており、これまでの実務経験を通じて「計数に基づく意思決定の重要性」を幾度となく実感してきました。
とりわけ、事業デューデリジェンスにおける内部環境分析においては、主観的な判断に頼るのではなく、客観的な数値を用いて事実を可視化することの重要性を強く認識しています。
ある案件では、クライアント企業から提供された商品別の販売データを週単位で整理し、販売数と粗利益を掛け合わせた単純な指標をグラフ化したところ、経営陣の評価とは異なる実態が浮かび上がりました。
たとえば、キャンペーンの目玉商品として推されていたA商品は、確かに販売数は多かったものの、実際には粗利率が極端に低く、利益にはほとんど貢献していなかったのです。
逆に、あまり話題に上っていなかったB商品が、販売数は控えめでも高い粗利率で安定した利益を出していたことが明らかになりました。
こうした“注目と実態のズレ”は、実務の現場では決して珍しいことではありません。
ファクトフルネスから学ぶ思い込みの危険

このようなズレが生まれる背景には、私たち人間が持つ「思い込み」や「印象」に引きずられる認知バイアスがあります。
人は、自分の経験や周囲の声、最近の出来事に過度に影響され、事実を正確に捉えられなくなることがあるのです。
この現象について深く考えさせられるのが、世界的ベストセラー『FACTFULNESS』(ハンス・ロスリングほか著)で紹介されている実験です。
著者らは、世界の現状に関する12問の三択クイズを、世界中のビジネスパーソンや知識人に出題しました。
結果、ランダムに選んだ場合の33%よりも低い、平均正答率17%という衝撃的な数値が示されました。
しかも、ノーベル賞受賞者や大学教授などの“知識階級”の方が、一般人より正答率が低かったというのです。
著者はこれを、人間の脳が持つ10種類の「本能的な思い込み」によるものと分析しています。
つまり、どれだけ知識があっても、認知にはバイアスがかかる。だからこそ、「感覚」だけで意思決定するのではなく、客観的な計数によって事実を確認しなければならないのです。
計数を活用した意思決定の5つのステップ
それでは、計数をどのように活用すれば、誤った判断を防げるのでしょうか。
私が現場で実践しているプロセスを紹介します。
感覚的な違和感も貴重な情報源です。まずはその直感に基づいて「何が問題か」を仮定します。
2.その仮説を検証するために必要な計数を洗い出す
会計データに限らず、生産性、稼働率、顧客別採算性など、課題に応じた計数が必要です。
3.該当する計数を実際に測定し、仮説と照合する
思い込みと計数が食い違っていないかを見極め、問題の本質を明らかにします。
4.課題が特定されたら、解決策と副作用の有無を検討する
打ち手の実行可能性や影響範囲を事前に十分精査します。
5.施策実行後は、効果を継続的にモニタリングする
改善が進んでいるか、再度計数で検証することで、施策の精度が高まります。
このようなステップを意識することで、意思決定の質は大きく向上します。
管理会計的な視点を加えることで「見える化」は進化する
経営判断に活かすべき計数は、税務申告用の会計データだけでは不十分です。むしろ、意思決定に必要な情報は、より現場に即した「管理会計的」な視点で収集されるべきです。
例えば以下のような指標が有効です。
・顧客ごとの採算性
・投下工数と成果の相関
・設備や人員の稼働率
こうしたデータを設計・取得・分析することは容易ではありません。
コストも労力も要します。しかし、「現場の感覚」と「計数の事実」をつなげる橋渡しとして、これほど効果的な手段はありません。
結論:測定なくして経営なし

稲盛氏が説いた「実学としての会計」、ロスリング氏が指摘した「人の思い込み」、そして私自身の現場での経験。
この三つから導かれる結論はシンプルです。
人は思い込む。だからこそ測る。そして、計数を根拠に意思決定する。
これこそが、あらゆる経営判断に求められる基本姿勢だと私は確信しています。
アタックスグループでは税務会計はもちろんのこと、税務会計数値の背景にある計数を活用した管理会計制度の構築支援や、設定した計数指標の改善状況をモニタリングするなどのサービスを提供しております。
こちらからお気軽にご相談ください。
筆者紹介

- 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング コンサルタント 水谷 友哉
- 事業会社の経理等を経験後、名古屋経済大学を卒業し、前職税理士法人を経てアタックスに入社。現在は、事業再生に従事する。クライアントやその利害関係者を少しでも良い状態にしたいという想いで支援を行う。