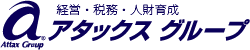私は、経営者や後継者を対象とする経営コーチです。先日、私がコーチングを行っている経営者の方から「岡田さんのコーチングを受けると、新たな気づきや新たな感覚を体感できる」とのお言葉をいただきました。
クライアントが「ありたい姿」や「望む場所」へと辿り着けるよう、日々伴走している私にとって、このお言葉はこの上ない喜びでした。
後日、その社長とのお食事の席で、改めてお尋ねしました。
「新たな気づきや感覚を得られると感じていただけたのは、私のどのような関わりがそうさせたのでしょうか?」
すると、社長は次のように答えてくださいました。
- 良き壁打ち相手であること
- 時間を守ること
- 思考を言語化・数値化・映像化してくれること
この社長はコーチャビリティ(※1)が高く、私に対しても率直なフィードバックをくださる方です。
今回も、私が日頃から意識し大切にしている事をズバリと言い当ててくださり、心の中で思わず「ヤッタ!」と叫んでしまいました。
※1:他者からのフィードバックやアドバイスを受入れ、能動的に自己成長に生かす能力。
この対話を通じて、コーチングの本質や効果的な関わり方について、改めて考える機会をいただきました。
ここからは、私なりの理解をもとに、ポイントを整理して解説します。
良き壁打ち相手「相手が話したい事を探る」
皆さんもご存じの通り、「壁打ち」とはテニスなどでよく見られる練習法で、壁に向かってボールを打ち、その跳ね返りを繰り返し返球するというものです。
コーチングの世界における「壁打ち」とは、コーチとクライアントが言語というボールを投げ合いながら、対話を通じて思考や感情を整理し、深めていくプロセスを指します。
私は、相手からボールを受け取ったら「同じスピード、同じ弧、同じ大きさ」で返すことを心掛けています。
これはオウム返しと似ていますね。
例えば、
この会話は一見成り立っているように見えますが、例えば、Aさんは表彰された喜びをBさんに聞いてほしかったとしたらどうでしょうか?
話の途中からBさんの話にすり替わってしまい、Aさんとしては喜びが半減し、他の人に伝えたいという気持ちもなくなってしまったかもしれません。
私が心掛けているコーチング流の「壁打ち」だと、次のようになります。
Bさんは、自分の事よりもAさんの心の内を探るために同じボールを同じ弧を描いて返球しています。
まどろっこしいと感じるかもしれませんが、聞いてほしいと思っているAさんはそう感じていません。
人は、「自分の話をきちんと聞いてもらえている」と感じなければ、心を開くことはありませんし、本音を語ってくれることもありません。
皆さんは、相手の立場に立った壁打ちをしていますか?
時間を守る「ゴール設定をする」
日本人社員が外国人社員から、「日本人は時間を守らないよね」と指摘をされたそうです。
日本人社員が、「そんなことはない。日本人は時間に厳しい人が多いよ。現に開始5分前ルールを守っているよ。」と返答すると、「そうじゃない。終わりの時間だよ。いつも会議時間を延長するじゃないか。」と返され、日本人社員は反論できなかったそうです。
議論が白熱し、時間が足りなくなれば延長もあり得ると考えていましたが、それでは時間がいくらあっても足りませんし、相手の時間を奪ってしまうかもしれません。
そこで、私が心掛けていることは、当日のセッションにおける「ゴール設定」を行うことです。
例えば、セッションの時間が2時間であれば、「2時間後にどのようになっていたいか」「この時間で獲得したいものは何か」を開始時点で合意するようにしています。
「ゴール設定」ができていれば、ゴールから逆算して、セッションのストーリーを組み立てることができます。
目的地となる港を決めずに大海原へ出港するのは、あまりにも無謀であり、それはまさに「納期の無い仕事は仕事ではない」という言葉と同じです。
たとえゴールまで辿り着けなかったとしても、それは決して失敗ではありません。
むしろ、無理やり結論を出そうとすることの方が、本質を見失ってしまう可能性があるため、その場合は、次回の課題としコミットメントにすればよいのです。
皆さんは、会議や面談のゴール設定をしていますか?
思考の言語化・数値化・映像化する「思考をより具体的に」
コーチングでは「答えは相手の中にある」という格言があります。相手も気づいていない能力や可能性を引き出すのがコーチングです。
質問を繰り返し、クライアント自身が頭で考えた事を言葉にし、相手に伝える。
これを繰り返すことでクライアントの頭の中に「オートクライン(※2)」の状態を起こすのです。
コーチングの究極の目的は、相手の頭の中に「オートクライン」を起こすことといっても過言ではありません。
※2:言葉にして話すことで、自分の考えや気持ちに気づく現象で、気づきや問題解決のヒントを自ら導いている状態。
私はこのオートクラインを促すために、対話の言語化→数値化→映像化を多用しています。
コーチングは互いの対話(言語と言語の往復)から始まります。セッションの初期段階では、まだ思考が整理されず、粗削りな言葉が飛び交うこともよくあります。
例えば、
私はセッション時の必需品として、直接会って行う対面セッションの場合は、ホワイトボードを利用し、オンラインの場合は、ペンタブレットを利用しています。
対話を最も重要視していますが、対話の中で浮かび上がった思考は、すぐに消えてしまいます。
そこで、思考を言葉として「視える化」することで、双方の共通言語として共有することができます。
例えば、我が社の利益状況について話し合う場合に、ある人は「売上総利益」を、ある人は「経常利益」を想定して話していたとしたら、会話はかみ合いません。
このような場合には、「何の利益について議論するのか」を明確にし、合意を取ったうえで会話を進めるべきですね。
その為に、ホワイトボードに言語化して可視化し、共有しています。
更に問題の所在を探りたい場合、2軸4象限やピラミッドストラクチャー、バリューチェーンを書き出して映像化することでお互いの対話のズレを補正しています。
皆さんは、言葉の空中戦を避け、可視化していますか?
まとめ

上手く機能しているコーチングの特徴を、事例を交えてご紹介しました。
本内容を知識として蓄える(Input)だけでなく、ぜひ、今日からできることを実行(Output)してみてください。
コーチングの資格がなくても、コーチングは可能です。前述のコーチャビリティが高い人ほど、コーチングの効果は大きいため、コーチングが有効に働く可能性のある方に対して実施してみてください。
アタックスでは、「アタックス経営コーチング」サービスをご提供しております。
ご興味のある方は、こちらからお気軽にご相談ください。
筆者紹介

- 株式会社アタックス 主席コンサルタント 一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ 岡田 昌樹
- 経営者や後継者そして経営幹部を対象とするビジネスコーチ。特に「財務コーチング」を得意とする。アタックスに入社してから2016年までは税務コンサルタントを主業務とする。関与した顧客数は延べ約200社。2016年からは税務業務に加え経営計画立案業務に携わると同時に、コーチングを取り入れた経営相談業務に携わる。ビジネスコーチとしてお付き合いしたクライアント数は約40人、コーチ経験年数は約6年。