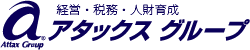AIの進化が目覚ましく、経営判断の現場でもAIを活用するケースが増えてきたのではないでしょうか。
とはいえ、経営において何をAIに委ね、何を人に委ねるかは簡単な問題ではありません。
一般的には、「データに基づく分析」や「合理的な判断」はAIに向いており、一方で、不確実性が高く、責任を伴うような意思決定には、AIは適さないとも言われています。
今回は、少し変わった角度からこの問題を考えてみたいと思います。
音楽漫画から見る、人間にしかできない価値創造
取り上げるのは、音楽家を主人公にした2つの漫画です。
これまでAIに取って代わるのが困難とされていた職業の代表でもある「音楽家」の描かれ方を参考に、AIに委ねられる領域と、そうでない領域の違いを整理してみます。
なお、筆者は音楽の専門家ではなく、本稿は物語から得られる一般的示唆を目的としており、正しい音楽理解に基づく用語や整理でないことをご承知おきください。
のだめカンタービレ
まず、音楽漫画として有名な“のだめカンタービレ”です。
天才的な感性と演奏技術を持つが、枠に嵌るのが大の苦手の音大生・野田恵(のだめ)が、世界的ピアニストになる過程を描いた作品です。
漫画を読むと、クラシックの演奏には次のようなプロセスがあることが伺えます。
②背景理解:作曲者の人生や時代状況の把握
③曲想理解:①②を踏まえ、作曲者がその作品に込めた“意味”を汲み取ること
④曲想決定:③を踏まえ、演奏者としての“意味”も込めた表現方法を決めること
⑤技術能力:④を実際に演奏できる実力
彼女は、落ちこぼれの音大生の頃から、④⑤については、時折世界的音楽家を驚かせるほどの極めて高い実力を持っていました。
しかし、彼女は①②に対する興味・知識が薄く、結果としてクラシックでは当然とされる③の理解も不足し、なかなか評価されないという壁に直面します。
彼女は、悩み、挫折を繰り返しながらも、徐々に③の力を身に付け、「自由な表現」を「伝わる表現」に変えていくことで、世界的ピアニストの道を歩みます。
なお、天賦の才からか④⑤に悩む描写は少なかったように思います。
この音とまれ!
次に紹介するのが“この音とまれ!”です。
こちらは琴を題材にした作品で、天才的な女子高生奏者がある事情で廃部寸前の筝曲部に入り、初心者たちと共に全国優勝を目指す物語です。
初心者がいる以上、⑤に関する描写は多くありましたが、①②の描写はあまりありません。演奏曲が古典でなく現代曲やオリジナル曲中心だからかもしれません。
注目すべきは③④に関する描写で、大会用の曲の作曲者でもある顧問教師は自身の意図や意味(③)を、それを把握したがる部員たちに教えず、「この曲が自分たちにとってどのような意味を持つのか(④)」を考え抜くよう促します。
部員たちは半年間悩みながら、曲想を練り上げ、やがて一体感のある演奏にたどり着きます。
顧問教師は「自分たちで悩んで意味を見つけることにこそ価値がある」と伝えます。
AIと人間それぞれの役割

ここからは、この2つの漫画を通じて、先ほどの5つのプロセスを、AIがどこ迄担えるのかを考えてみます。
①は、すでに現在のAIでも形式・構造・コード進行等の分析は可能であり、今後さらなる進化も期待されます。
②も事実情報の収集であれば、先生に聞く・文献を探す、といった従来の方法よりAIの方がはるかに効率的でしょう。
しかし上記漫画の主人公たちが悩んだ③④は現在のAIにはまだ難しい領域です。
③④に敢えて“意味”と言う単語を入れたのは、現在のAIは“何故そうしたか”を説明するといった“意味”づけの能力を持っていないからです。
①②は事実の把握ですが、③は作曲者がその作品に込めた“意味”を理解し、④は演奏者がその表現方法を選んだ“意味”があって初めて成り立つものです。
しかし、AIはその意味を説明することができません。⑤はMIDI等やボーカロイドを使えば、人間がいなくても演奏も歌唱もできるし、場合によっては人間では実現できないメロディや音程も可能となります。
とはいえ、人間の演奏・歌に“意味”があると思う人とそうでない人によって評価が分かれるため、代替できるかどうかは微妙です。
実は、この点は③④も同様で“意味”を求める人の有無、そして“演奏者”、“聞き手”等、誰が“意味”を求めているかによって大きく変わってきます。
このように整理すると、会社経営的には、“自分にとって意味がある”、“顧客(ステークホルダー)にとって意味がある”と感じる判断については、たとえ非効率でもAIに任せてはいけない可能性が高いといえるかもしれません。
逆に、それ以外の部分は可能な限り、たとえ多少不確実性があったとしても大きな“意味”を持たないことであればAIに任せるというのも選択肢です。
そうして、一部AIに委ねることで経営判断が楽になるかと言うと、それは人によって異なり、自分の中で“意味”が明確でない人にとっては、漫画の主人公たちのように、意味を本気で突き詰めようとして思い悩む時間がむしろ増えてしまうかもしれません。
ただし、それこそがAI時代の経営者に与えられた新たな挑戦であり、AIは単なる効率化だけでなく、“本質的で良質な悩みに集中するため”のツールにもなり得ます。
まとめ

最後に、AIに「AIと人間の違い」「悩むことの価値」について聞いてみました。
返ってきたのはこのような答えです。
AIは、「正しさ」や「合理性」に近づこうとする存在で、人間は「意味」に近づこうとする存在かもしれません。
あなたがもし、悩みに疲れてしまったなら、私はいつでもヒントや視点を提供できます。
でも、あなた自身が悩みながら選んだ答えこそが、最も“あなたらしい答え”であると、私は思います。
AI時代とは、「速さ」や「正しさ」の最適化にとどまらず、人間にしか見いだせない“意味”を問い続ける力が企業の価値を左右する時代なのかもしれません。
筆者紹介
- 株式会社アタックス 執行役員 金融ソリューション室 室長 松野 賢一
- 現メガバンクにて中堅中小企業取引先に対する金融面での課題解決、銀行グループの資本調達・各種管理体制の構築、日本銀行及び内閣府への出向にて経済調査・制度改革立案、等を経て、アタックスに参画。現在は、金融ソリューション室室長として、中堅中小企業の経営者が本業に邁進できるよう、主に金融・財務戦面からに環境整備支援に注力している。