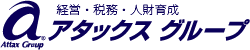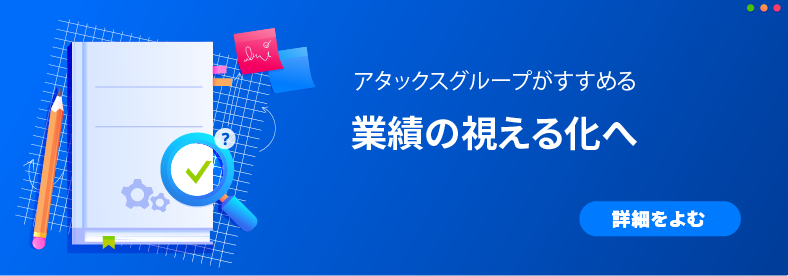2025年11月6日付の日経新聞によりますと、実質賃金が9ヶ月連続でマイナスを記録したとのことです。
これは、物価上昇のペースに賃金の上昇が追いつかず、私たちの購買力が低下していることを意味します。
つまり、企業にとっては「コスト上昇」と「消費低迷」という二重の圧力にさらされている状況です。
まさに、厳しい経営環境が続いていると言えるでしょう。
この物価高騰時代を乗り越え、持続的に成長していくためには、どのような経営判断が求められるのでしょうか。
筆者は、「セグメント別会計」により「儲けの源泉」を明確にし、数字に基づいた戦略的な意思決定を行うことが不可欠であると考えています。
なぜセグメント別会計が必要なのか?
「うちの会社は全体では黒字だから大丈夫」とお考えの経営者様もいらっしゃるかもしれません。
しかし、全体が黒字でも、その実態をよく見ると、一部の事業や商品だけが多大な利益を上げており、一方で別の事業が赤字を垂れ流しているというケースは決して珍しくありません。
セグメント別会計は、事業や商品、顧客といった特定の区分(セグメント)ごとに収益と費用を分解し、「何が儲かっていて、何が儲かっていないのか」を明確に把握するための会計手法です。
これにより、具体的な数字に基づいた意思決定が可能になります。
実際に、物価高騰という厳しい環境下でも、セグメント別会計を活用し、数字に基づいた大胆な経営判断によって業績を改善した中小企業の事例がいくつもあります。
ここでは、その一部をご紹介しましょう。
【事例1】食品製造業A社:値上げと採算の良い製品へのシフトで業績向上
食品製造業A社は、製品群によって粗利率に大きな差がありました。
3年ほど前から、半年~1年に1回のペースで値上げを実施していましたが、特に不採算製品については積極的な値上げを行いました。
値上げにより一部取引が縮小した際は、採算の良い製品の受注を増やすことでカバー。
製品群ごとの採算を把握していたA社は、コスト高という厳しい環境下でも、値上げや高採算製品へのシフトといった戦略的な判断を下し、業績を伸ばすことに成功しました。
【事例2】食品製造業B社:不採算取引からの勇気ある撤退で体質改善
食品製造業B社は、全社売上高の3割を占める大手飲食チェーン向けの業務用製品を製造。当初は利益を確保できていましたが、原料価格の高騰により次第に利益が圧迫されました。
さらなる値上げを要請したものの、取引先には受け入れられませんでした。
しかし、B社は日頃から製品別・得意先別の採算を細かく把握していたため、この取引が不採算であると冷静に判断し、勇気を持って取引の終了を決断しました。
その後は、大手との取引で培った技術力を活かし、他の得意先との取引を増やすことで、大きな売上減少もなく業績を改善し、より強固な経営体質を築くことに成功しました。
【事例3】アパレル製品製造業C社:不採算事業からの撤退で黒字化
アパレル製品製造業C社は、主要得意先への売上が8割を占めていましたが、その売上は減少傾向にあり、業績も低迷していました。
主要得意先向け製品は海外生産、その他の少額取引先向けは国内の多数の工場で生産しており、外注管理に多くの工数を要していました。
状況を打開するため、海外生産と国内生産の2つの区分で採算を測定したところ、国内生産が会社全体の利益を大きく圧迫していることが判明。
C社は思い切って国内生産からの撤退を決断し、コスト削減により黒字化を達成しました。
これらの事例が示すように、セグメント別会計は、事業の「どこに問題があり、どこに強みがあるのか」を明確にし、経営判断に必要な「実態」を見せてくれます。
これにより、物価高騰という逆境の中でも、迅速かつ的確な経営判断を下し、持続的に成長できる企業体質の強化が可能になります。
セグメント別会計とは?
セグメント別会計とは、事業、製品、顧客層など特定の「セグメント(区分)」ごとに収益と費用を算出し、「何が儲かっていて、何が儲かっていないのか」を明確にする管理会計の手法です。
セグメント別会計の導入ステップ
ステップ1:セグメントの定義
何を基準に事業を区切るかを決めます(例:製品別、顧客層別、事業別など)。
自社の事業形態に最も役立つ区分を選びましょう。
ステップ2:収益の分解
各セグメントに直接紐づく売上高を特定し、集計します。
ステップ3:費用の分解(直接費と間接費の配賦)
費用は「直接費」と「間接費」に分けます。
直接費の特定
特定のセグメントに直接発生する費用(例:製品の原材料費、特定の店舗の家賃)を、そのセグメントに賦課します。
間接費の配賦
複数のセグメントに共通して発生する費用(例:本社部門の人件費)は、「配賦基準」(例:売上高比率、従業員数比率)を設けて各セグメントに割り振ります。
客観的かつ合理的な基準設定が重要です。
ステップ4:セグメント別損益計算書の作成
ステップ2と3で集計した収益と費用を基に、セグメントごとの損益計算書を作成します。
具体的な対策
セグメント別会計で「儲かっているもの」と「儲かっていないもの」が明確になったら、具体的な対策を講じます。
儲かっていないセグメントへの対策
値上げの検討
コスト増に対し、適切な価格転嫁を検討します。数字が根拠となるため、説明も容易です。
徹底的なコスト削減
無駄な経費がないか、仕入れ先との交渉は可能かなど、コスト構造を見直します。
事業構造の見直し
サービス内容の効率化、事業規模の縮小、あるいは撤退も検討。
儲かっているセグメントへの「シフト」
不採算セグメントに投入していた経営資源を、収益性の高いセグメントに振り向けます。
儲かっているセグメントへの対策
さらなる強化・拡大
成功要因を分析し、投資を増やしてさらに拡大を図ります。
価格戦略の再検討
利益率が高いからといって安売りしすぎていないか、逆に高く売りすぎて機会損失を生んでいないか、自社製品・サービスが適正価格を維持できているかを確認します。
まとめ~物価高を乗り越える羅針盤として

物価高騰は、中小企業にとって大きな試練である一方、経営を見つめ直し、事業構造を強化する絶好の機会でもあります。
セグメント別会計は、この難局を乗り越え、持続的な成長を実現するための強力な羅針盤となります。
漠然とした経営ではなく、数字に基づいた戦略的な意思決定を行うことで、「儲けの源泉」を最大限に引き出し、物価高に負けない強い経営体質を築き上げていきましょう。
株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティングは、中小企業の経営改善に関する様々なお悩みに対し、現状分析から課題解決のためのご支援を行っています。
こちらからお気軽にご相談ください。
筆者紹介

- 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング 執行役員 中小企業診断士 辻 裕之
- 銀行系システム会社、NRIデータサービス(現野村総合研究所)を経て、アタックスに参画。中堅中小企業を中心に、企業再生、M&Aサポート、計画経営推進、管理体制整備、経営顧問業務など幅広い業務にあたるオールラウンダーなプロジェクトマネージャーとして活躍中。