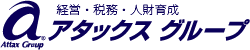2021年の経済センサス(最新)によれば、「菓子・パン小売店」は全国に55,447店ある。
ちなみに、2012年の経済センサスを見ると、その数は62,007店であったので、この9年間で6,560店、率にして10.6%の減少である。
単純計算ではあるが、この間、毎年、全国各地で729もの「菓子・パン小売店」が消滅したことになる。こうした菓子・パン小売店の減少は、市場の縮小、つまり生活者のパン・お菓子離れとは到底思えない。
というのは、その販売額を見ると2012年の1兆6546億円が、2021年には1兆6619億円と、微増とはいえ、業界全体の販売額は増加しているからである。
また、家計調査年報で、世帯の菓子やパンの平均購入額を見ると、年度により若干のばらつきはあるものの、菓子もパンも小幅ながら右肩上がりで増加しているからである。
その意味でいえば、「菓子・パン小売店」の衰退の要因は、コンビニエンスストアや食品スーパー、さらにはショッピングセンター等での菓子・パンの販売の影響もあるとはいえ、最大の要因は、顧客にとっての買い場としての魅力度格差が、拡大しているからといえる。
事実、全国各地を歩いてみると、顧客から高い評価を受け続け、好業績を持続している「菓子・パン小売店も」、少なからず存在しているからである。
その1社が、兵庫県甲陽園の「ケーキハウスツマガリ」である。同社の本店は、阪急甲陽線の終着駅である甲陽園駅から徒歩数分の商店街の一角にある。
お菓子好きの人ならば、大抵の人が知っている有名店であるが、本店のお店は、わずか17坪である。しかも、お店の1階は、前を走る道路より一段低いまるで半地下のような店舗である。
「ケーキハウスツマガリ」の創業は、今から38年前の1987年、創業者は津曲孝氏である。
津曲孝氏は、宮崎県の山間の小さな村で誕生したが、家庭に恵まれず、中学校を卒業すると、学生服を着て、風呂敷包み1つで、東京のある小さな企業に就職している。
どんな仕事でも一生懸命取り組む津曲氏を見込んだ支援者に、その後、お菓子屋さんを紹介され、はじめてお菓子の業界で仕事をすることになった。
津曲氏は、製菓の専門学校等で学んだこともなく、また力のある菓子職人に手取・足取りで教えていただいたこともなく、下積みの期間が長かった。
しかしながら、めげず、誰よりも働き、就業時間後も、残った原材料等で、お菓子作りに取り組むなど懸命に努力し、菓子職人としての高い評価を得るまでになった。
その後、職場で知り合った奥さんの激励もあり、著名なお菓子屋さんをスピンアウトし、実質2人で、現在地で創業したのである。
同社の今日までの成長・発展の要因を一言でいうと、規模や業績など一切負わず、本コーナーのテーマ通り、世のため人のためになる経営にぶれず取り組んできたからである。
その紹介したい具体的内容は、美味しいお菓子の訳、素材への強いこだわり、一人ひとりの顧客への真摯な対応、障がい者の雇用、創業者の魅力、さらには、地域社会への熱き想い等、多々あるがここでは、紙面の都合で、地域社会への熱き思いに絞り紹介する。
ケーキハウスツマガリの本店は、創業時も社員数320名となった今でも同じ場所である。しかもリニューアルはしても、建物は創業時と同じである。
また、店舗もあえて多店舗展開をせず、大丸梅田店と大丸神戸店には出店しているものの、それは出店したかったからではなく、大丸から強く請われたからである。
それどころか、今でも東京などの大型店から破格の好条件での出店要請があるが、その全てを断っている。
これほど地域にこだわる理由の1つは、創業者である津曲氏が「甲陽園という地域への熱き思い」「創業時の熱き想い」「本日開店の心」「お世話になった地域社会への御恩返し」を一時も忘れないがためである。
加えて言えば、創業時支えてくれ、今は加齢を重ねた地域のお客さんの思い出の場所で、あり続けたいからである。
それゆえ、百貨店に請われ出店しているとはいえ、百貨店で販売しているのは、焼き菓子・クッキー・チョコレートだけで、生ケーキは本店でしかあえて販売していない。
余談であるが、もしも、生ケーキをこれら百貨店で販売したならば、ツマガリの売上高は数倍に増加すると思われる。
とはいえ、数名の社員数から現在は320名の社員数にまで拡大しているので、創業の店舗が狭過ぎるのは当然である。
こうした疑問は、ケーキハウスツマガリの周辺の道路を歩いてみると直ぐ解ける。つまり、その周辺には大・中・小と、様々ではあるが、ツマガリの看板を掲げた建物が、やたら多いのである。それはまるでツマガリ通りである。
それら建物は、ツマガリの製菓工場や試作工房・倉庫・社員の福利厚生施設等で、その数は15ヶ所を超えている。
これらは、いずれも、もともとは他店の小売店舗や事務所、あるいは、個人住宅であったが、後継者がいなかったり、不採算で廃業したり、居住者が高齢で亡くなられたり、遠方の子供のもとに引っ越されたりと、様々な理由で、空き店舗・空き家になってしまった建物ばかりである。
しかも、これら建物は購入したものが半分、賃貸契約が半分である。それは所有者の希望に沿うためである。
加えて言うと、所有者から提示された購入金額や賃貸価格は、相手の言い値・希望する条件で購入や賃貸契約をしたのである。
効果・効率や、自分の都合、さらには業績等を重視し考えれば、本店を他地域に移転したり、隣接地の確保や高層化であろうが、敢えてしてこなかったのである。
アタックスグループでは、1社でも多くの「強くて愛される会社」を増やすことを目指し、毎月、優良企業の視察ツアーを開催しています。
視察ツアーの詳細は、こちらをご覧ください。
筆者紹介

- アタックスグループ 顧問
経営学者・元法政大学大学院教授・人を大切にする経営学会会長 坂本 光司(さかもとこうじ) - 1947年 静岡県生まれ。静岡文化芸術大学文化政策学部・同大学院教授、法政大学大学院政策創造研究科教授、法政大学大学院静岡サテライトキャンパス長等を歴任。ほかに、「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞審査委員長等、国・県・市町村の公務も多数務める。専門は、中小企業経営論、地域経済論、地域産業論。これまでに8,000社以上の企業等を訪問し、調査・アドバイスを行う。